目次
まえがき:AGI時代に訪れる“人間の問い直し”
AGI――汎用人工知能。ついにそれが現実味を帯びてきました。 あらゆる作業を代替し、あらゆる意思決定を最適化する存在。これが社会に登場したとき、私たち人間は何を失い、何を問われるのでしょうか?
「これからの人間の役割は?」と問われると、つい職業の話や労働市場の話に飛びがちです。 でも、本当に問うべきはそこでしょうか? 人間は、社会にとって“役に立つ存在”でなければいけないのでしょうか?
AIが「正しい判断」をすべて肩代わりするようになった時、残されるのは“無駄で無意味に見える”行為かもしれません。 でも、その“無意味さ”の中に、実は人間らしさの本質があるのではないでしょうか?
第1章:「幸福」は処理不能なノイズである
AGIは圧倒的な知能で人間を凌駕します。どんなに複雑な計算も、瞬時にこなします。 でも、たとえば「日が沈む瞬間に涙が出そうになる」といった感情を、彼らは理解できるのでしょうか?
私たちの幸福は、とても雑で、あいまいで、非論理的です。 なぜか心が震える。理由は説明できない。でも確かにそこにある。 そうした“ノイズのような幸福”は、AGIにとって最も処理困難なタスクなのではないでしょうか。
わかりやすく言語化された願望――「お金がほしい」「モテたい」「ラクしたい」など――は、むしろAIが一番得意とする領域です。 最短距離で、最適な解決策を出してくれる。
けれども、「なぜか心に残る風景」や「理由もなく惹かれる人」のように、うまく言語化できない幸福は、AIの予測をすり抜けます。 それって、実は人間の最後の砦ではないでしょうか?
第2章:「なんか心地よい」はAIにとってブラックボックス
先日、とあるドキュメンタリー映画を見ました。 主人公のカップルは、1台のバイクで世界一周を目指す旅に出ます。寒さや暑さ、雨や雪に凍え、トラブル続き。 快適とはほど遠い一見すると幸福とは真逆の体験が続きます。なのに、なぜかその姿に心を打たれたのです。
それは、合理性では説明できない“心地よさ”でした。 見ているこちらまで、凍える風や孤独を追体験しているような感覚。 そして、そこに「幸福の種」のようなものを感じたのです。
こうした“なんか心地よい”という感覚。 データ化できず、論理にも還元できず、しかも他人と共有するのが難しい。 AGIにとっては、まさにブラックボックス。
逆に言えば、私たちが“AIにできないこと”を模索するなら、こうした「あいまいな幸福」の解像度を高めることがヒントになるかもしれません。 自分にしかわからない心地よさ、自分でも説明できない感動。 それらを大切にすることが、「人間らしさ」の核心を守る行為ではないでしょうか。

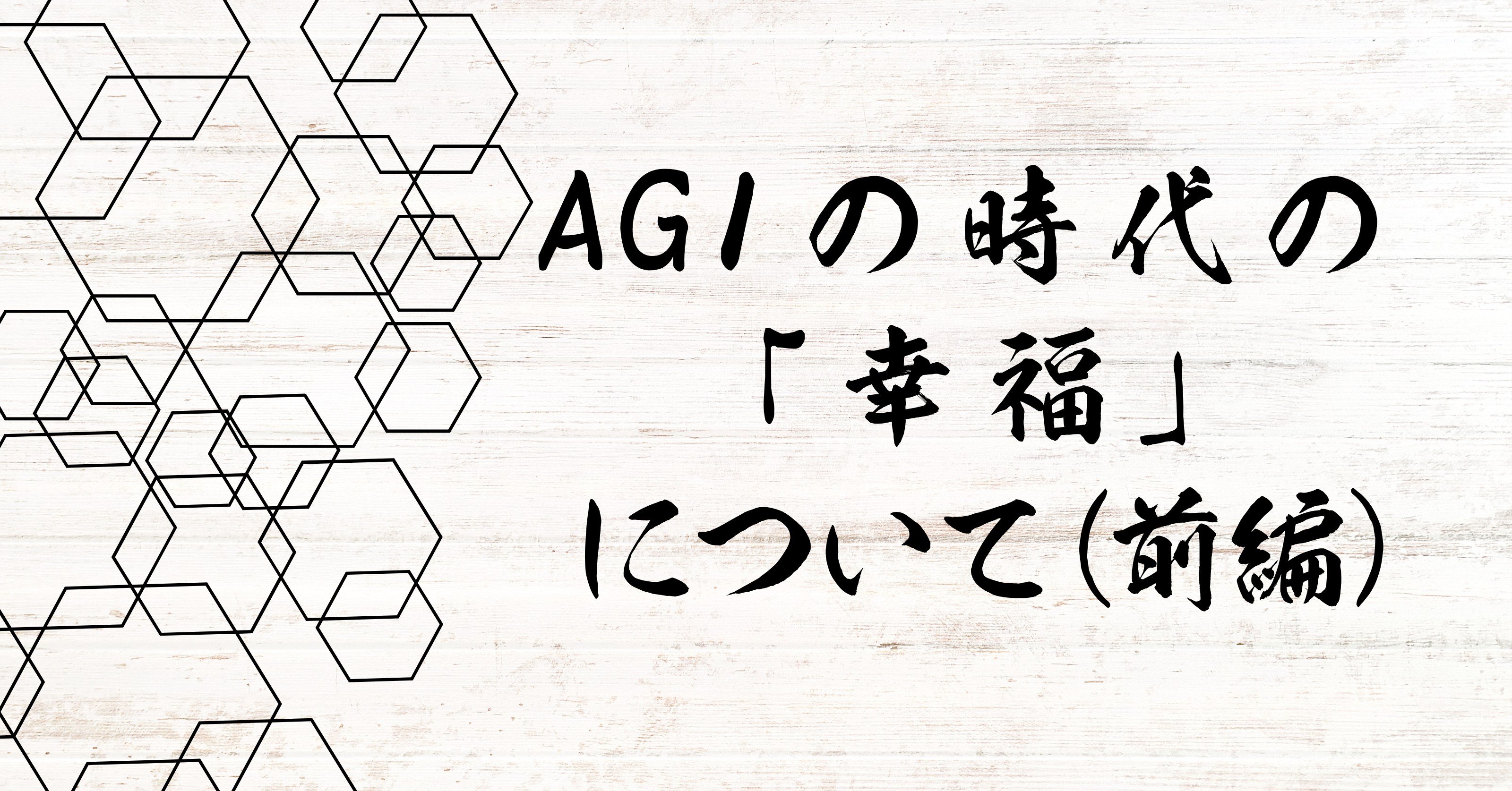
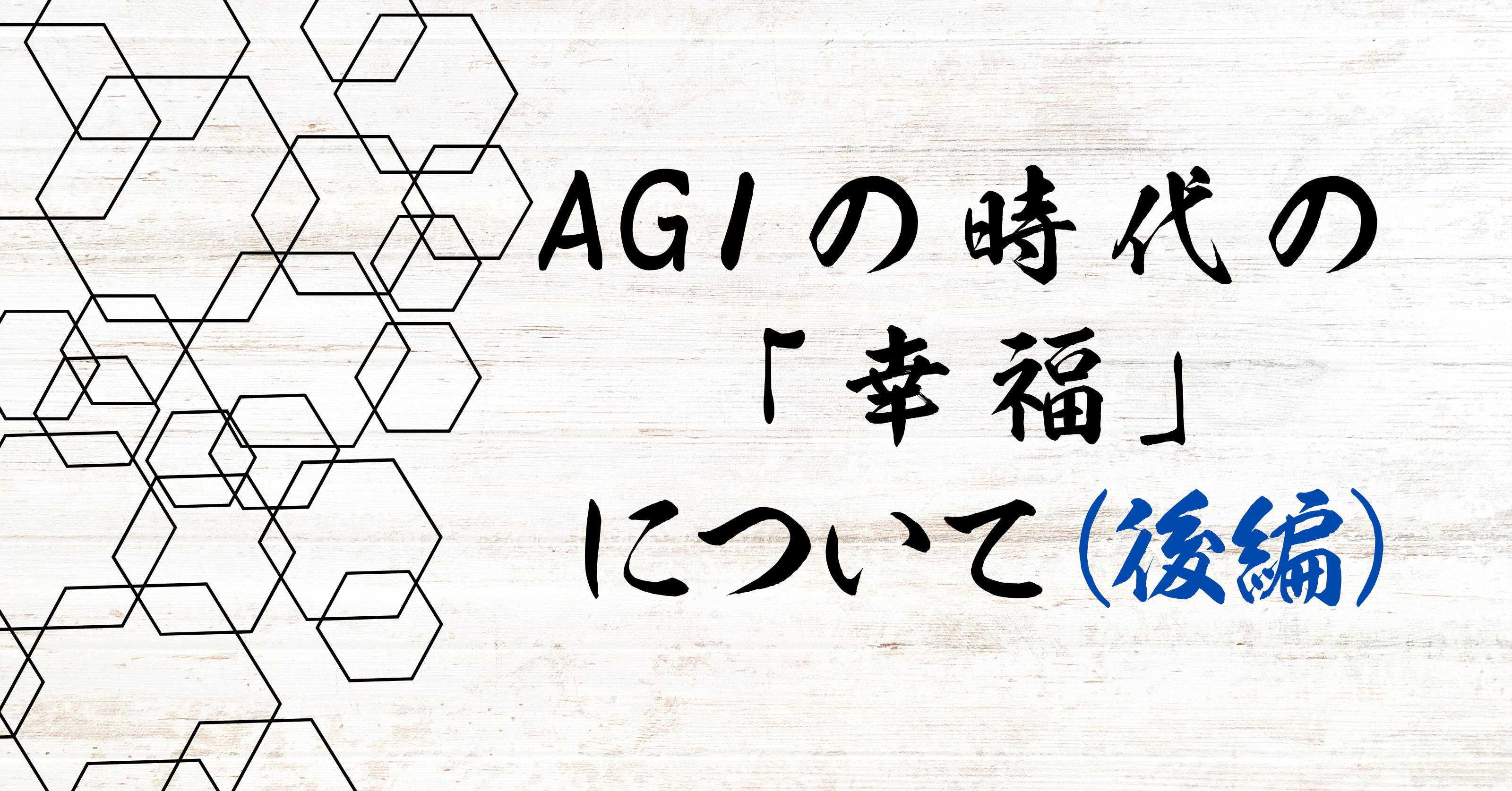
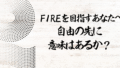
コメント