- はじめに:動物化する労働者たち
- 1. 資本主義と「欲望のパターン化」
- 2. FIREという「欲望の脱構築」
- 3. 「消費からの逃走」は可能か?
- 4. FIREと「人間の物語性」
- おわりに:「自分のストーリー」で生きること
はじめに:動物化する労働者たち
「なんのために働いてるんだろう」
そんな問いを、心のどこかに抱えながらも、黙って電車に揺られてオフィスに向かう人たち。
SNSとサブスクで退屈を紛らわせ、疲れたら居酒屋とコンビニスイーツ。
気がつけば、与えられた快楽のサイクルを反復するだけの存在になっていないだろうか。
この状態を、東浩紀は「動物化」と呼びました。
彼が言う“動物化”とは、欲望を自ら生み出すのではなく、用意されたメニューから選び、ただ快適さを維持する状態です。
自分で意味を問い直すことなく、定型的な人生スクリプトに従って生きる。
FIREを目指すという行為は、この“動物化”から抜け出す試みに見えます。
1. 資本主義と「欲望のパターン化」
現代の資本主義は、もはや“モノを作る”よりも“欲望を設計する”ことで回っています。
広告、ランキング、レビュー、SNSのトレンド。
私たちは「選んでいる」と思わされながら、実際は“選ばされて”います。
働き方も同じです。
正社員というステータス、住宅ローン、35年ローン、子どもの習い事。
「普通の人生」が“用意された欲望”の集合体にすぎないのだとしたら、それをなぞることに何の意味があるのでしょうか?
2. FIREという「欲望の脱構築」
FIRE(Financial Independence, Retire Early)は、単なるお金の問題ではありません。
それは、欲望のリセットであり、物語の書き換えです。
「働かずに生きる」ことが重要なのではなく、「何のために働くのか」を再定義すること。
そこに“物語”がなければ、たとえ経済的に自由になっても、再び資本の奴隷になります。
自分の言葉で自分の人生を語れるか?
これが、FIREに踏み出す前に問うべき最大の問題です。
3. 「消費からの逃走」は可能か?
FIREの実践者たちの中にも、“消費しない快楽”をひたすら求める人たちがいます。
例えば、節約、ミニマリズム、投資によるキャッシュフロー。
しかし、それが“別の形の資本主義ゲーム”に過ぎなければ、本質的な脱出とは言えません。
東浩紀が言うように、「意味を見失い、ただ快適さを追い求める動物化」は、表面的には豊かでも内面は空虚です。
つまり、FIREとは「消費から逃げる」ことではなく、「意味を取り戻す」ための戦いなのです。
4. FIREと「人間の物語性」
人間には“物語”が必要です。
私たちはストーリーで自分を理解し、他者と関わり、社会に居場所を見つけます。
ところが、現代社会ではこの物語が貧困化しています。
正社員→結婚→マイホーム→定年という“古い神話”はすでに崩壊していますが、
その代わりとなる“生き方のストーリー”は提供されていません。
FIREは、その空白を自分で埋める作業です。
「自分は何者で、どう生きたいか」。
その問いに答える物語を自分で紡げるかが鍵になります。
おわりに:「自分のストーリー」で生きること
FIREを語る上で最も重要なのは、「いくら貯めるか」ではなく「どう生きたいか」です。
そしてその問いに答えるには、「自分の頭で考える」ことが不可欠です。
自分のストーリーを生きるという覚悟。
それこそが、東浩紀が「動物化からの離脱」として説いた、現代人に必要な知性です。
FIREとは、資産ではなく“思考”の話。
誰かのメニューではなく、自分だけのレシピで人生を作ることなのです。

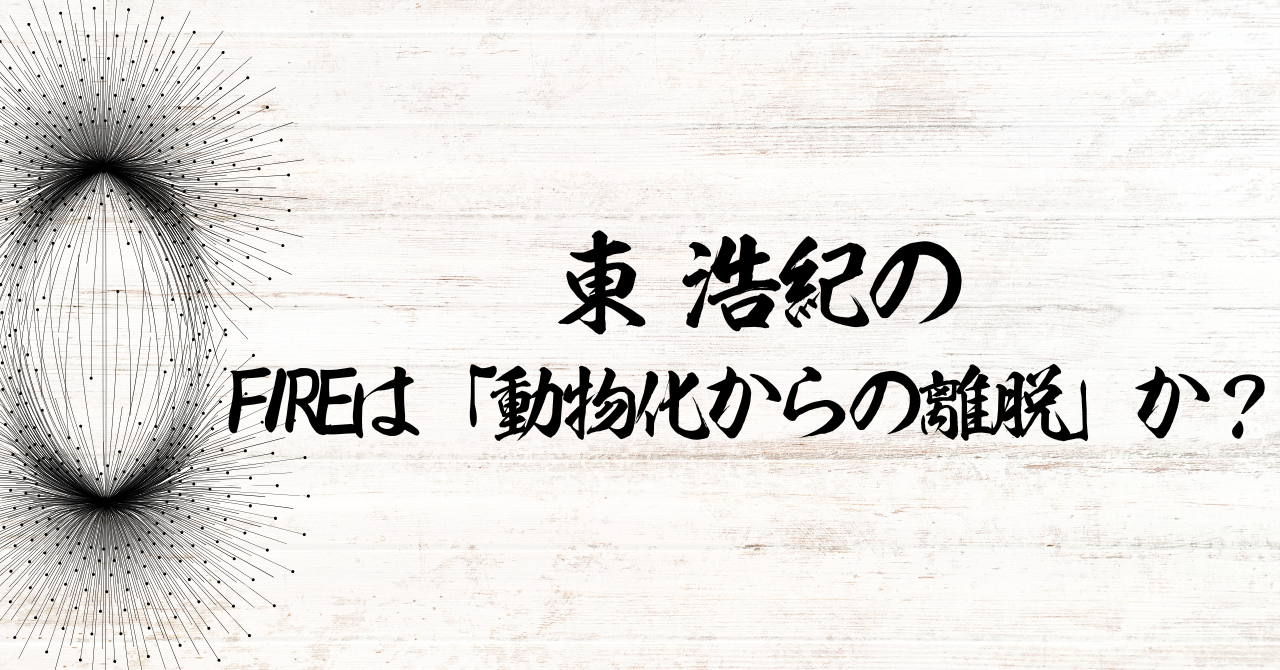
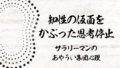

コメント