目次
“怠け者=悪”という道徳観
私たちは子どもの頃から「怠けてはいけません」「真面目に頑張りましょう」と教えられてきました。
そして、遊んでばかりのキリギリスには厳しい視線を向け、コツコツ働くアリに拍手を送ります。
気づかぬうちに、“怠け者=悪”という道徳観が私たちの中に根付きました。
でも考えてみてください。
“怠け者”って誰にとっての“悪”だったのでしょうか?
他人の人生を生きず、自分のペースで時間を使い、自分の感性で生きている人が、なぜ“悪”なのでしょう?
誰がその価値観を必要としたのか?
答えは明白です。
それは、他人を働かせたいと考えていた人たち――つまり“支配者層”です。
国家、宗教指導者、資本家、工場主、学校経営者……彼らにとって都合が良いのは、「自ら進んで働く民衆」です。
いちいち命令せずとも、勝手に早起きして汗を流し、時間どおりに出勤して生産する。
そんな“従順で自己管理能力の高い労働者”こそ、彼らにとっての理想でした。
だからこそ、労働を神聖化し、怠惰を罪とする倫理観が体系化されていったのです。
プロテスタント倫理しかり、近代の教育制度しかり、メディアの成功者神話しかり。
「怠けるな、頑張れ」という言葉の背後には、「お前は労働力だぞ」という無言の圧力が込められているのです。
学校という“労働者製造装置”
この価値観を効率的に刷り込むために用意された装置――それが「学校」です。
チャイムで行動を決め、時間割で生活を管理し、テストで順位づけされ、集団行動で同調圧力を学ぶ。
これはもう、小さな“社会の予行演習”です。
学校は「学問を学ぶ場所」ではなく、「ルールに従うことを学ぶ場所」だったのではないかと、今になって思います。
そして、その先にある「就職」という通過儀礼を経て、私たちは完全な“労働適合者”になります。
「遅刻しない」「文句を言わない」「与えられた課題をこなす」――これが“優秀”とされる社会。
その一方で、「やりたいことがない」「何が楽しいかわからない」と迷子になる大人が量産されていきました。
そして今、私たちは何を信じているのか
ここまで来て、ようやく問い直すべき時がきたのではないでしょうか?
「怠け者って、本当に悪なのか?」と。
SNSでは「意識高い系」が持て囃され、「朝活で差をつけろ」「成功者は努力している」みたいな言葉が溢れています。
でもその裏で、他人の人生を生きることに疲れ果て、自分を見失う人も少なくありません。
私は声を大にして言いたい。
「怠けることは悪ではない」と。
むしろ、自分の内なる欲求やリズムに従って、何もしないことを選べる人は、すごく“人間らしい”存在だと思います。
キリギリスの歌は、誰かに評価されるためのものではありません。
ただ、今この瞬間を生きる喜びが音に乗っただけなのです。
その姿に“無意味の価値”を見出すことができたら、あなたの中の道徳観はもう一歩先へ進んでいるのかもしれません。

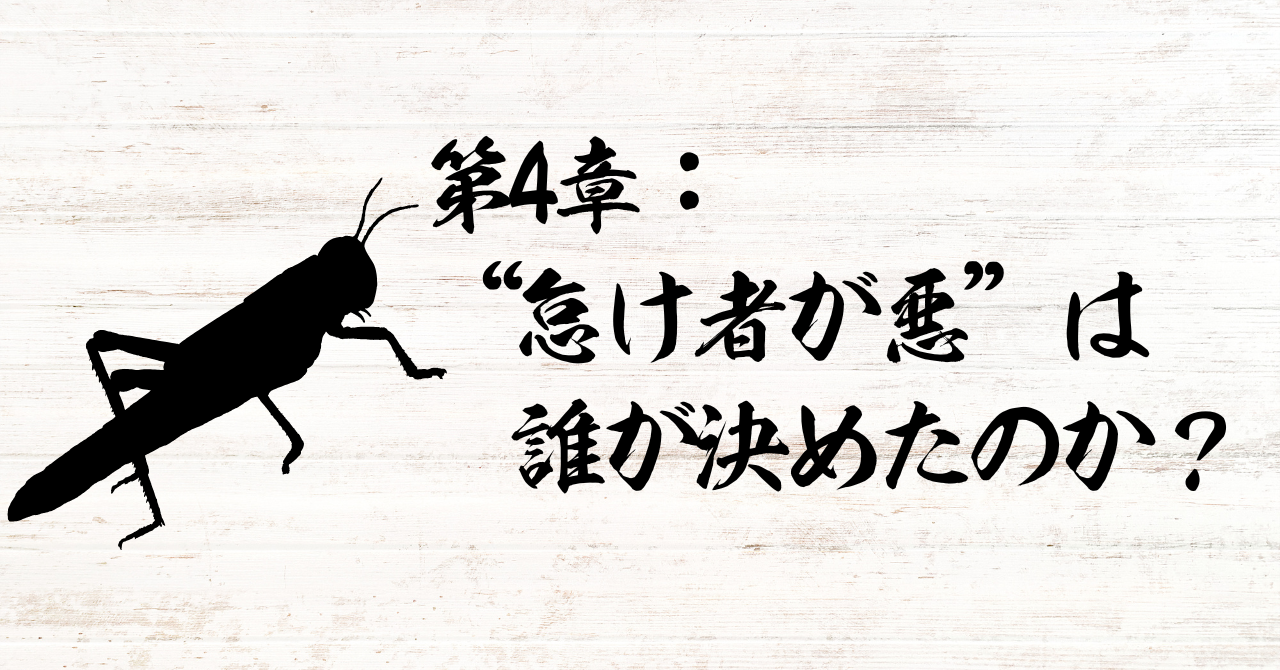
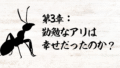
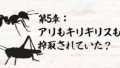
コメント