目次
第1章:自由とは「誰かに見張られないこと」ではない
「自由に働きたい」「会社に縛られずに生きたい」――FIREを志す人の多くがそう口にします。 けれども、自由とは本当に「誰にも命令されない状態」のことなのでしょうか? 内田樹が言うように、自由とは「自分の選んだ規律に自発的に従っている状態」を指すのです。
つまり、誰の指図も受けないことが自由ではなく、自分が信じた原理に自分の意思で従うことこそが「自由な状態」です。 他人の命令から逃れたとしても、代わりに「お金」や「他人の目」や「SNSのフォロワー数」に縛られていたら、 それは単なる“檻の引っ越し”にすぎません。
FIREとは“自由になること”ではなく、“どんな不自由を自分で選ぶか”という問題です。 自由という言葉の甘さに酔っていると、自分で選んだ不自由すら、誰かに押しつけられた不自由に見えてくる。 その瞬間、自己責任という名の幻想が私たちを押し潰します。
自由には責任が伴います。誰にも文句を言われないということは、誰にも助けてもらえないということでもあるのです。 「自由を手に入れる=孤独を抱える覚悟を持つ」ということ。 この覚悟がないと、FIRE後に自由を持て余し、かえって不自由になる人も少なくありません。
第2章:会社が“依存装置”になる構造
日本の会社というものは、単なる「雇用契約」を超えて、人生全体を包摂する“依存装置”になっています。 給料だけじゃありません。人間関係、承認欲求、アイデンティティ、老後の保証……。 ほとんど全部を、会社に預けっぱなしです。
「会社辞めたい」と言いながら辞められないのは、そこに自分の全てを預けているからです。 ある意味、それは“親から自立できない子ども”と同じ構造です。 会社が正しいかどうかなんて問題ではない。 ただ、そこにいれば生きていける。考えなくていい。誰かが保証してくれる。 その“楽さ”が、会社からのドロップアウトを阻む最大の理由なのです。
組織にとっては、社員が「自分では何も決められない」ほうが都合がいいのです。 なぜなら、判断を上に委ねることで、責任を分散できるからです。 だからこそ、企業はわざと社員に“考えさせない”ように設計していることが多いのです。
FIREは、経済的自立の前に「心理的な断乳」から始まります。 会社という“ぬるま湯”の中に、どれだけ自分が耽溺していたかを直視するところから始まるのです。 そして、それを断ち切るのは「根性」ではありません。冷静な自己認識と、小さな一歩の積み重ねなのです。
第3章:「自立」は手続きであり、感情ではない
多くの人が「自分はまだFIREできる状態じゃない」と言います。 資産が足りない、家族が心配、年齢的に遅い――理由はいろいろ。 でもその実、大半は「自立が怖い」だけです。
内田樹の言う“自立”とは、「社会に依存しながらも、自分の意思で制度と付き合う力」です。 自立とは、孤独であることでも、完璧であることでもありません。 必要なときは誰かに頼り、制度に身を委ねる。 でも、その選択を“自分の意思”でやる。そこに、自立の本質があるのです。
「自立した人」というのは、誰にも頼らずに生きている人ではありません。 むしろ逆で、助けてもらうことを“自分の意思”で選び取ることができる人のことです。 つまり、FIREを目指す人が学ぶべきは、金融商品よりもまず「制度との距離の取り方」なのです。
親との距離、会社との距離、世間との距離。 それらを「一歩引いて見る力」こそが、真の“経済的自由”の前提です。 そのためには、まず自分がどんな構造に依存しているかを知ること。 FIREとは、資産を築く旅であると同時に、「自分の思考の癖を修正する旅」でもあるのです。

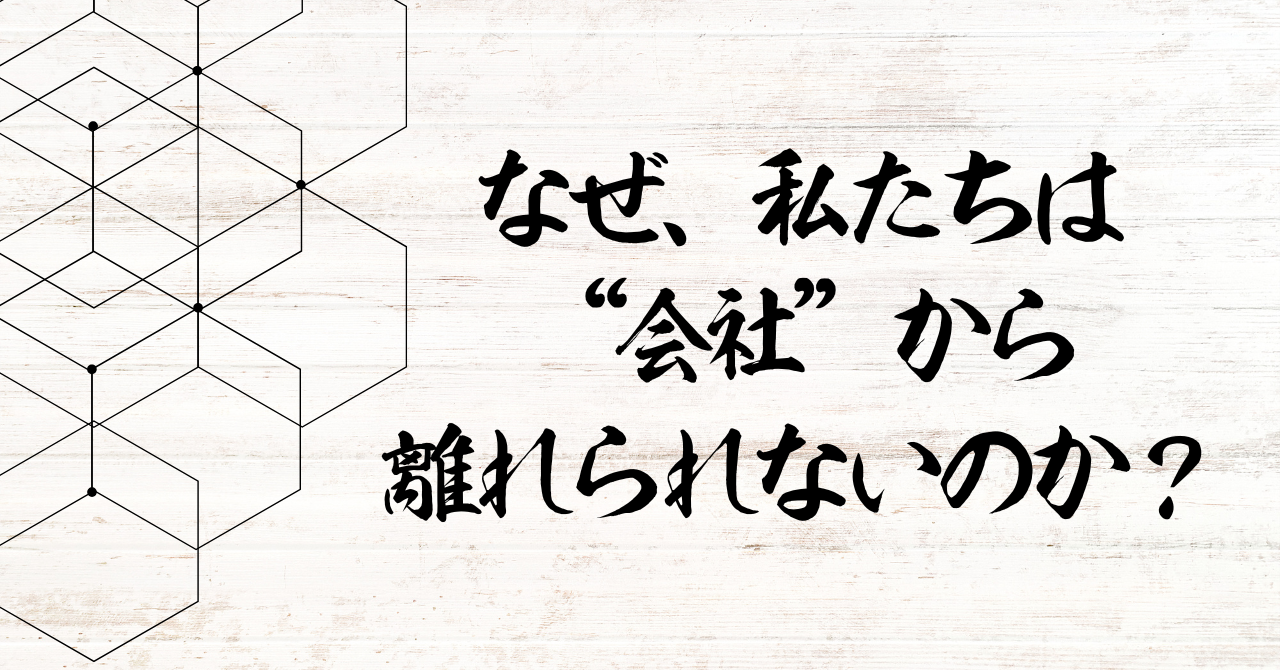
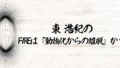
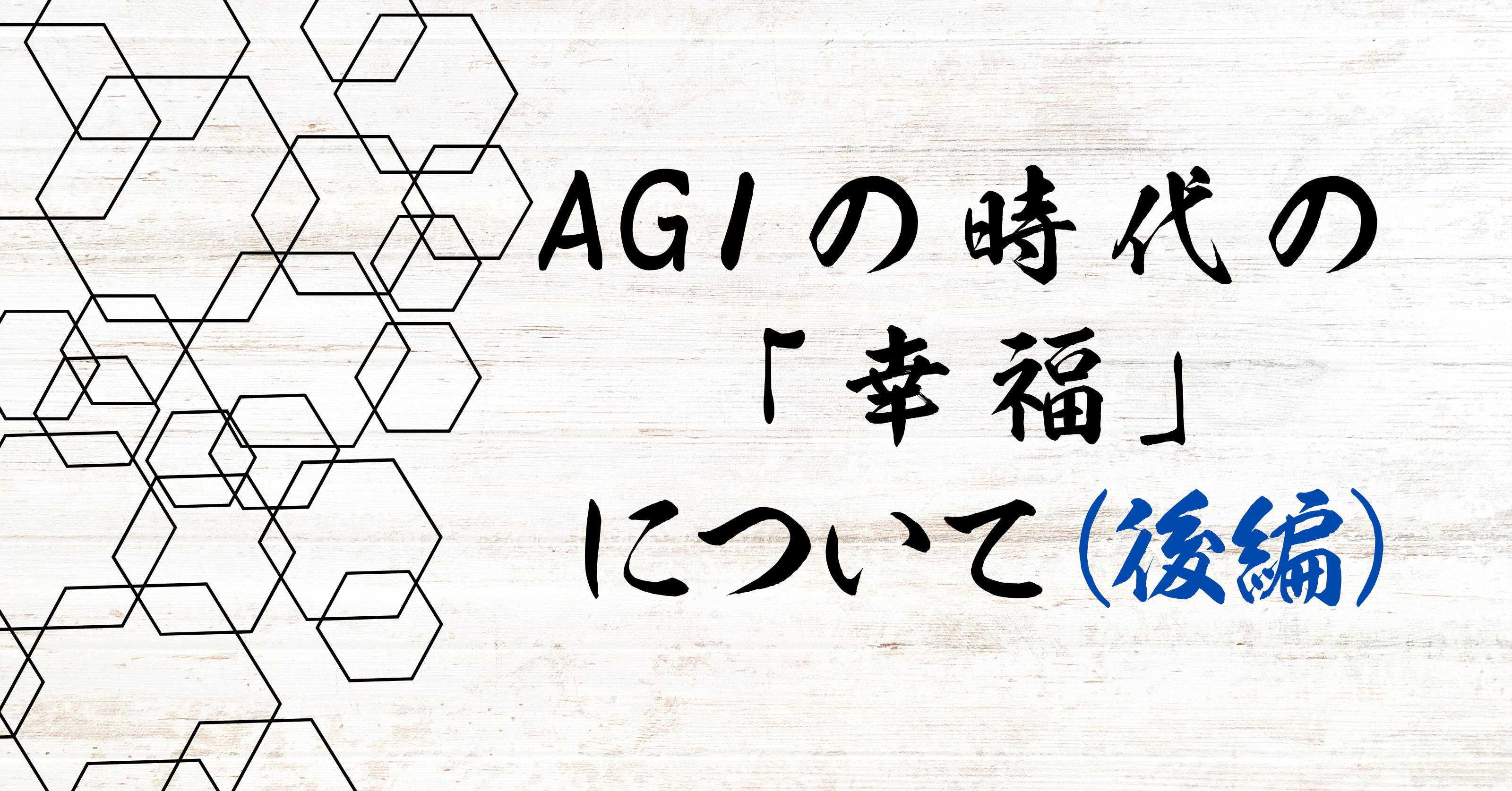
コメント